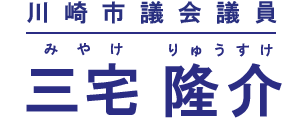永禄10年(1567)、信長は美濃を平定した。あの桶狭間の戦いの勝利から僅か7年足らずである。
信長は「美濃」の地名を「岐阜」と改めた。「岐」は古代中国において天下を治めるものが挙兵する地「岐山」からとり、「阜」は指導者論の祖ともいうべき孔子が生まれた「曲阜」からとって岐阜とした。同時に信長はこのころから「天下布武」の印を使用している。要するに、この日の本の国を統一し、武士が一元的に統治する新たな国家体制につくりかえる。そうした明確なビジョンのもとに、この地を統一事業の活動拠点として位置づけたのである。因みに、現在の47都道府県において、歴史上の人物が命名した都道府県は岐阜だけである。
信長は統一事業の中期目標として機内の制圧を目指した。畿内制圧のために必要な事業は上洛である。そのための準備を着々と進めてもいた。
断っておかねばならないが、ここでいう上洛とは天下統一のことではない。京にのぼっただけでは日本全土を制覇したことにはならない。ただ、上洛を果たして京を実行支配できたとすれば、天皇から京の統治権を委任されたことになり、その政治的な意味は極めて大きい。群雄割拠の戦国時代、それぞれの武将がこぞって上洛を競いあったのはそのためである。
さて、政治的上洛を実現するためには軍事的に畿内を制圧しなければならない。信長はまず、背後を固めなければならなかった。
上洛事業にとって背後となる東側には、三河国(愛知県北部)がある。その三河には松平信康がいる。後の徳川家康である。家康とは自分の娘である五徳を家康の嫡男に嫁がせて、すでに同盟関係を強化している。いわゆる政略結婚であった。
この時期の家康は、死に体の今川家をめぐって甲斐(山梨県)の武田信玄と凌ぎを削っていた。今川家は、桶狭間の戦いで信長に迎撃されて以来、義元の子・氏家が家督を継いでいたが、家勢は喪失し、もはや風前の灯火であった。
その今川を武田のみならず、相模国(神奈川県)の北条も狙っている。ハイエナが獲物に群がるようにして、武田・北条・徳川は、こぞって今川領を奪おうとしていたのである。
このことから、大国である武田・北条と二正面で対峙しなければならない家康にとっても、飛ぶ鳥を落とす勢いの信長との同盟はありがたいものだった。また信長領の同じく東側で隣接しているその武田も、前に徳川・北条、後ろに上杉を抱えて動きがとれない。だからこの時期の武田は、信長の上洛事業にさしたる影響を及ぼさない。
以上のことから、信長の上洛事業推進にあたって、東側に問題はない。
次に北側の近江(滋賀県北部)だ。近江には浅井長政という機内有数大国の領主がいた。が、この浅井家にも、すでに妹のお市を嫁がせ同盟関係が構築されている。
東と北は盤石だ。あとは南側だが、ここは岐阜と京を結ぶ補給線を南側から脅かす北伊勢(三重県北部)にあたる。
こちらは、前年の春から勇臣・滝川一益に命じて伊勢北境の諸城を攻略させている。この北伊勢には大きな大名は存在しなかった。神戸氏、長野氏、工藤氏、細野氏、関氏などの諸氏が乱立していた。これに対し信長は、巧みな攻城戦を展開するとともに、息子を養子にするなどの外交戦によって、永禄11年(1568)の2月にはこれらの地域を制圧した。
東、北、南、と三方を完全に固めた信長がめざすものはただ一つ京しかない。
ただ、三方を固めたといっても、それはただ単に軍事上の体制が整っただけにすぎない。信長という偉人は、そのことだけで拙速に兵を動かすほど短慮な男ではない。
事業であっても、戦争であっても、共同体を率いる指導者には大義がいる。いかに盤石な軍事力を有し、背後を固めた信長にとっても同然だった。
しかし、その大義を既に信長は獲得していた。その大義とは、
“足利義昭の擁立”
である。
少し説明調になり退屈だが、ご容赦願いたい。
足利義昭とは、室町幕府第13代将軍の義輝の弟である。兄の義輝は、なんと家来であった三好氏や松永氏によって殺されてしまう。実弟であった義昭は危うく難を逃れて京都を脱出した。
兄を失い、軍事力を持たない義昭は、越前の国(福井県付近)の朝倉家を頼った。朝倉は大きな大名でもあったし、室町体制を重んじる格式高い家柄でもあったからである。義昭はその朝倉家の力を利用し、三好や松永が擁立した14代の傀儡将軍を追い落とし、自らが15代将軍に就任する意欲を燃やしていた。
しかし、あてにされた朝倉は、義昭の期待に応えるほどの意欲もカネも兵力も持っていなかった。朝倉は義昭をもてあましていた。
義昭とその側近たちは失望した。そんなとき、側近のひとりである明智光秀は信長に目をつけた。つまり義昭のブランド力と信長の政経軍の実力とを結びつけようとした。日の出の勢いであった新興企業と、今はなき名門ブランドを引き合わせたようなものであった。
大義はあるが軍事力を持たない義昭と、軍事力があっても大義がない信長の利害の一致である。
“天下布武”という大義は、なるほど織田家中をまとめることはできても、満天下と万人を納得させてることはできない。対内的に通用する大義と対外的に通用する大義とに大別した場合、義昭擁立は後者に属する。
ともかくも、信長のもとにこの上ない大義がころがり込んできたのである。
時代とは、それを動かそうとするものに地獄ほどの辛苦を与えるが、そのひきかえとして、ときに百年に一度ほどの幸運を授けるものなのである。
さて、永禄11年(1568)の9月7日、3万7千の軍勢を従えて、これまで基本構想・基本計画の段階であった信長の上洛事業は、いよいよ具体的な軍事展開に移った。
上洛を憚る敵は、近江(滋賀県)南部を領有する名門の六角氏。六角氏は前衛基地である箕作城をはじめ、居城である観音寺城などで徹底抗戦を試みるが、ついに力尽きた。畿内を支配していた三好、岩成、池田も次々に信長軍に撃滅される。
結果、9月26日には上洛を果たし、10月2日には、池田勝正の居城である摂津池田城を陥落させ、畿内制圧を達成してしまった。おどろくべきことに、僅か一ヶ月での畿内制圧である。
凄まじいほどのスピードである。六角も三好も池田氏も、それぞれ畿内を取り仕切るほどの勢力ながら、なぜにここまで信長に完敗したのか、ということを考えざるをえない。
まず、信長の入京に抵抗したこれら諸勢力は、信長の組織改革の本質を理解していなかったことが主因となろう。
なんといっても、9月といえば、これから稲作の収穫期を迎える時節である。こんな時期に、出陣することなど、当時の軍事常識では考えられない。前述のとおり、信長兵は兵農分離されている。つまりは農繁期や農閑期に関係なく出陣できる。
また、この8年前に今川義元が3万の兵を引き連れて居城である駿府城を出陣したとき、すべての軍勢が居城を出発するのに、なんとまる3日間かかったのだが、このたび信長が岐阜を出発するのに、わずか10時間程度しか要さなかった。おそるべきスピードである。それも兵農分離なる信長の組織改革の所産といっていい。
要するに彼らは、信長の組織改革に完敗したのである。
ところで、今年のNHK大河ドラマは「義経」だそうな。
配役への不満などもあり私は視聴していないのだが、その義経の従兄弟にあたる木曾義仲が平氏を京から追い払い上洛したときの話である。
義仲の軍勢は、都で狼藉の限りを尽くし、京の市民と朝廷を困らせた。女を犯し、子供を連れ去り、店を取り壊し、銭を巻き上げては、酒に溺れたのである。その後、義経に追討されることになる。
そのことが京都市民には記憶の片隅に色濃く残っている。
信長上洛の情報を得た京都市民は、おびえ動揺した。
気性果敢な信長が上洛するに際し、木曾義仲の再来、という噂が京を駆け巡ったのである。
しかし、そうはならなかった。
信長は、京都市民との摩擦を避けるために、軍の主力を郊外に留め、自らは僅かな警護を引きつれ東寺に着陣した。また、都の治安を維持できる程度の兵だけを京に入れた。敗残兵の掃討のための措置である。
都人は、信長軍の軍規厳格さに驚いた。
後年、信長とも親交のあった公家の山科言継の日記によると、信長上洛の前の京都の様子がよくわかる。その日記には、
「都の人々は、妻子や家財を思い思いに疎開させている。自分も貴重品を御所に移した」
と記されている。
だが、信長軍の軍規があまりにも厳格に保たれていたため、疎開した人々もほどなく都に戻り、京都は再び賑わいを取り戻した。
さらには、東寺に陣取る信長のもとに連歌師の里村紹巴(さとむらじょうは)が拝謁したときには、里村の祝いの句に対し、返礼の一句を詠んでいる。この一件を伝え聞いた京都の町衆は、信長が無骨な田舎大名などではなく、知識と教養を兼ね備えた人物であることに感嘆したという。
この一件などは、多分に政治的でパフォーマンス的でもあるが、共同体を率いる指導者としては必要不可欠な感性である。
ともかくも、信長による畿内制圧は、その組織改革の斬新性と決め細やかな外交努力の結果であったことに疑う余地はあるまい。