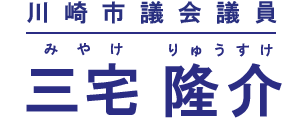いわでものことだが、当時、「五徳」は典型的な台所用具のひとつであった。炭火などの上に置いて鉄瓶などを載せる器具のことである。
信長はそんな台所器具の名前を自分の娘にさえつけている。
そのことは、かれが名門家やその種の家系の血筋に対して、これといった魅力や関心をほとんど示さなかったことのひとつの証かと思われる。あるいは台所用具のように飾らない親しみやすい存在として、その女性をふかく寵愛していた証とも解釈できる。
名門家の女性を避けたという点では、徳川家康も似ていて、かれもまたその種の女性をできるだけ遠ざけた。名門・権門家で育った女性は、とかくその存在自体がある意味での政治性を帯びてしまうし、あるいはその女性自身がいずれ政治的な野心野望を抱きかねず、またその血筋を利用して「事」を謀ろうとする何者かさえ出現しかねない。
事実、人類の歴史がたとえ男性史的側面をもっていたとしても、ときに女性が権勢を振るい天下を左右したことも否定できない。
女性が権勢を振るう、といった場合、たいがい二つばかりのパターンに分類できる。
ひとつはその女性がその王朝の前線に立ち、いわば女帝的存在として直接的に権勢を振るうケースであり、もうひとつは権力の影に潜んだ為政者の母や妻が、間接的に政(まつりごと)に介入するケースである。
前者の代表例は、あるいは推古天皇であり、世界史的規模でいえば古代エジプトの女王・クレオパトラだったろう。日本おける後者の代表例は秀吉の側室であった淀姫としておこう。
後者の場合、たいてい、その王朝や国家の衰退をはやめてしまうことが多い。
豊臣政権から秀吉が去った後、跡取り秀頼の母であった淀君と、豊臣家臣団筆頭の徳川家康とのあいだで、熾烈な確執がはじまることになる。結果、関が原の役、大坂の役をへて、豊臣家は滅亡する。
淀姫の幼名は「茶々」という。
近江の名門・浅井家の出で、しかも四方(よも)様(四方(どこ)からみても美しい女性のこと)と呼ばれた信長の妹・お市の方の長女でもあった。
信長の死後、自分こそが織田家の正当なる後継者であることを満天下に知らしめたかった秀吉にとって、信長の血をひく淀君を側室にする意味は多分に大きなものであったろう。
しかし秀吉の死後、その淀君の政治的存在が豊臣家を滅亡たらしめたひとつの要因であったことを考えると、歴史の皮肉さを感じざるをえない。
名君とは、将来起こりうるあらゆる危険をできうる限り事前に排除してこそ、その名に値する。その点、信長も家康も歴然とした名君であったといっていい。
信長が政略結婚の対象とした濃姫をいまひとつ愛しきれなかった理由のひとつも、このあたりに起因するのかもしれない。むろん、想像の域をでない。
ところで、信長の子供の数から推計すると、かれには7人、8人の側室がいたことになるのだが、信長が魅せられる女性の多くは、おそらく豊かな母性とあふれる品格とを併せ持った女性であったように思えてならない。
そのことは、かれが吉乃とお鍋という二人の未亡人を愛したという事実からいくぶん想像できる。
それから、信長の同姓偏愛の対象として、よく森蘭丸があげられる。あるいはそうかもしれない。
が、果たしてそれだけであろうか。
蘭丸に限らず、信長という人は多くの男(家臣)たちから愛されていたように思えてならない。むろん、その愛とは必ずしも性愛でない。
たとえば、秀吉の信長に対する忠義と忠勤は、並みの部下が上司にするそれをあきらかに超えている。出世欲に駆られた男など、古今東西に腐るほど存在したわけで、秀吉の捨て身の忠義心は、その種の平凡な出世欲だけによる産物ではあるまい。
中国の古典では、
「士は己を知るものの為に死す」
という。
この場合、士とは秀吉をいい、己を知るものとは信長のことを指すのだろう。
次号につづく・・・