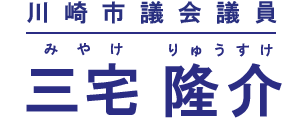信長は、父の死後、いよいよ家督を継ぐことになる。だが、それまで父・信秀が築き上げた軍事体制を否定した。
父の信秀は、他の大名がそうであったように、領内の百姓兵を農閑期に召集して、軍事行動を展開した。
百姓兵は、各村落ごとに編成される。
たとえば、ひとつの村落が百人ちかい小作人を兵隊として戦場に送り込むとする。
その百人の内訳は、馬に乗った騎兵が10名程度、鉄砲兵が5名程度、弓もち兵が20名程度、槍もち兵が30名程度で、他の30~40名は荷物や旗を運びつつ、戦場ではひたすら石を投げて自軍を援護する。
こうした一つの村落兵を束ねた者を、いわゆる豪族という。この豪族の連合体がひとつの大名軍を構成していたのである。
といって、この時代、戦国大名なるものは、絶対的権力の上にその地位が保証されていたわけでもなかった。
大名は絶対権力者ではなく、これら諸豪族の盟主にすぎなかったのである。
たとえば、ある大名が政治的失策を犯し、他の大名家にその領地支配権を奪われたとする。それでも、先祖伝来の土地を有する豪族たちとすれば、盟主が変わったにすぎないのである。失政を犯した旧主君とともに、末路をともにしようとする豪族はまず皆無である。
つまりは、各大名は盟下の諸勢力(諸豪族)の機嫌を常に伺っていなければならなかった。
いわば大名とは、『農協』の理事長的存在といっていい。
武田信玄は、
「人は石垣、人は城」
と言った。
人材力こそ国力であると宣言し、他の大名のように城や砦などの軍事施設をつくらなかったことは有名である。
しかし、その実は農協の理事長として、ひたすら仲間内の融和活動に専念したにすぎなかった。
それに対し、信長の目指す国家は、天下布武である。
くりかえすが、それは、武士が一元的に支配する絶対王政でもある。
ただの盟主では、絶対王政は実現できない。
当然、豪族依存型の現行体制は否定されざるを得ない。信長は豪族連合に依存しない独自の軍事機構をつくることになる。
まず、土地に縛られない百姓兵に頼らず、お金で雇われる職業軍人を募集した。日本史上、はじめて登場するサラリー軍人だ。
しかし、当時、お金で雇われるような人たちは、世上、真っ当な人たちではない。いわば、流民、札付き、盗賊の類である。
信長の生まれた中世においては、真っ当といわれた人は皆、必ず何らかの組織・共同体に属していた。
たとえば、お百姓さんは村落共同体に属し、商人は座に属し、僧侶神官はそれぞれの寺社に属していた。そのいずれの共同体にも属せない人たちは、まさに流浪の民であった。
後の豊臣秀吉などは、信長に拾われる以前、村落に属することもできず村を飛び出し、座の認可を受けることもできず潜りの商人として針を販売して歩いていた。が、結局、針座の商人たちに不正商いが見つかり、捕まって集団リンチをうけて死ぬ思いをしている。彼はまさに、流浪の民の典型だったのである。
信長は、こうした流浪の民をかき集め、組織改革を試みる。
現代風にいえば、中卒や高校中退の元暴走族あがりを採用し、それまで長く勤めた東京大学卒のエリート社員を窓際に追いやり、新しい事業をはじめたようなものである。
もし、現代、このような二代目若社長がいたなら、次期株主総会で社長退陣に追い込まれるのではあるまいか。
事実、信長は、弟の信行と凄まじい家督争いをしている。織田家に代々勤めるエリート豪族にしてみれば、信長改革など到底受け入れることはできない。
かれらが、良識的価値観を持ち合わせた弟の信行を社長に推そう、と考えるのも当然であったろう。
父・信秀の葬儀では、正装に身を包み品よく哀しみを表現した弟に対し、当時では考えもつかない服装で、突然、式の途中にあらわれた。お焼香をわしづかみし、父の位牌に投げつける。
「父上、成仏なされよ」
とでも、言ったであろう。
家督争いの大切な時期に、このような行動を採る信長にただ者ならぬ何かを感じざるを得ない。しかし、これこそが、彼流の哀しみの表現だったに違いない。
ともかくも、かれは改革を断行し、それまでの社内エリート集団をことごとく敵にしたのである。
それでも、新しい事業がひとつの結果を収めることができれば、内紛もいずれおさまるものであろうが、そうはならなかった。信長のつくったサラリー軍団は、ことのほか弱かったのである。戦えば、連戦連敗。負けるたびに新規雇用を図った。
それが、社内抵抗勢力を大いに勢いづかせる論拠となった。
それでも尚、彼はこの未曾有の弱小兵に固執した。それには、それなりの理由があったからだ。エリートたちにはそれが理解できなかった。なぜ信長が、そこまでして流浪の民を主力部隊にしようとするのか。