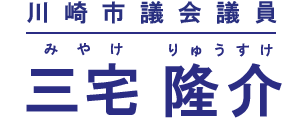信長は、お金で志願兵を雇い入れた。当時としては、ひどく画期的なことだった。
しかし、かれら傭兵軍団は、甚だ弱かった。それは何も、傭兵たちの訓練不足によるものではない。
では、なぜ弱かったのか、ということになる。
と、いうより、従来の百姓兵の方が、かれら傭兵団に比べ、より命がけで戦場に赴いていた、と言ったほうが正確な表現であろう。
ひとつの村落を代表して戦場に赴く百姓兵には、当然、家族がいる。
仮に、戦場で臆病風に吹かれ、敵前逃亡するようなことでもあれば、その兵の家族は村落において「村八分」となってしまう。
文明の進んだ今日においてさえ、排他的色彩を帯びた地域社会では、となり近所、あるいは村や町全体の“悪評”というものに、つねに怯えて暮らさねばならないことを考慮すれば、そのことの深刻さは容易に想像できよう。
また、合戦のとき、ある村落が陣取る部隊が真っ先に陣地陣形を崩してしまったとする。
「あのとき、一番最初に崩れたのは、あの隣村だ」
と、いうことになり、その村は近隣の村落からさげすまれ、あの村には水はやるな、という事になりかねない。ひとつの村落にとって、水争いも深刻な問題であった。
だからこそ、百姓兵は必死に槍働きをしたのである。けっして、大名や豪族たちへの忠誠心で命を懸けたわけではない。
しかし、残念ながら、信長が雇いし傭兵軍団には、帰すべき村落も家族もない。そのため、いざとなると、平気で信長を裏切り、戦場から姿をけしてしまうのである。
そこに傭兵軍団の弱さがあった。
当然、従来の百姓兵を組織する古き重心たちは、
「それみたことか、我らを遠ざけ、あのような流浪の者たちを信用するからこのようなことになるのだ。殿は頭でも狂われたか」
と、信長を批判する。
信長が当時の常識人に、
「大うつけ」
と、馬鹿呼ばわりされたのは、このためだ。
かれら現状維持派は、陰に陽に信長改革の断念を画策するのである。
しかし、天下布武の絶対王政を標榜する信長としては、一度掲げたビジョンを簡単に変更することはできない。
まさしく“臥薪嘗胆”としか言いようがない。
そもそも、お金で集いし浪人軍団が、戦えば弱かったことなど、あたりまえであったし、信長にとっても予測の範疇であった。
ここに、改革者・織田信長の根気強さと執念深さが、いかんなく発揮されるのである。
確かに、戦えば負けつづけ、負けては兵はどこかに帰え去った。
しかし、不足した兵は、またお金で雇えば集まった。これを根気強く繰り返した。繰り返すうちに、弱点が利点に変わった。
名将は弱点を利点に変える。それに対し、愚将はただひたすら成功体験を繰り返し、利点を弱点に変えてしまう。
信長は失敗体験を繰り返し、まさしく弱点を利点に変えたのである。
信長の戦略はこうだ。
敵の百姓兵が強いのは確かだが、農閑期にしか戦うことができない。ということは、逆に言うと、農繁期の敵城は、兵がほとんどいないことになる。わずかな警備兵がいる程度なのだ。
信長の傭兵軍団は、農繁期も農閑期も関係なく出陣でき、いつまででも戦える。
例えば、いかに弱小兵の傭兵軍団といえども、千人の兵力をもってすれば、10人そこらの警備兵しかいない城なら、たやすく落とすことができる。
敵方にしてみれば、
「信長、卑怯なり」
と、言いたいあたりだが、そもそも、事業経営においてもそうだが、新機軸というものは、つねに卑怯な発想から生まれるものである。
何よりも、百姓兵で構成された豪族連合との大きな違いは、信長の傭兵隊は、彼の号令一下、いつでも素早く行軍できたことであろう。
さらには、帰すべき村落を持たない兵であったればこそ、信長は、危険な戦闘地帯へも、容易に出撃命令をくだす事ができた。この点も見逃せない。
百姓兵は、村八分という村落の私的制裁を恐れて必死に戦うのだが、実際には、かれらを動員した大名や豪族たち自身が、ことのほか、百姓兵の死を恐れた。
百姓兵が平時における大切な農業生産者であった事が、その理由としてあげられる。
つまり、ひとりの兵を失うことは、ひとりの生産者を失うことになる。
また、村落共同体の地域福祉が成立していたので、ひとりの兵が死ねば、村落の地域福祉に多大な負担が生じる。過度な負担が重なれば、大名や豪族たちへの不満が高まり一揆や反乱の火種になりかねない。
結果、百姓兵を率いる大名は、生死のかかった一か八かの危険な戦場に、兵を突入させることだけは極力慎まねばならなかった。
それに対し、信長の雇いし流浪軍団には、仮に戦死したとしても、負担となる地域福祉もなければ、悲しむ家族もいない。俗っぽい言い方になるのだが、お金で雇えば、かぎりなく増員補充が可能であった。
この利点が、いかんなく発揮されたのが、前述の「桶狭間の戦」である。
信長の10倍の兵力を持ちながら、首を獲られることになる今川義元は、この一戦に際し、周到な準備と緻密な戦略を練りに練って臨んだ。
けっして、信長を甘くみたわけでも油断していたわけでもなかった。ただ、義元が誤ったのは、信長軍の行軍スピードが自軍のそれを遥かに凌いでいたことに気づかなかった点である。
信長が、なにやら怪しげなる者たちを集め、それらをお金で雇い入れ、新しい組織作りをしていたことは、義元も事前の諜報活動ですでに承知していたにちがいない。
しかし、そのことが、どのうような結果をもたらすか、というところまでは考えられなかったようだ。
いつの時代でも、官僚化したエリート集団にとっては、無学歴者による新しい試みは関心の対象とされがたいものである。
また、義元軍の本隊五千が桶狭間に駐留していた際も、信長軍の主力部隊二千がすぐそこまで刻々と迫っていたことを、派遣していた偵察隊や捜索隊からの報告で義元は知っていたはずだ。ただ、その部隊を信長という大将自らが率いていることまでは察していなかったかもしれない。
しかし、義元と今川幕僚たちは、次のように考えた。
(近づいているとはいえ、たった二千の兵で五千の今川本隊に突撃をかけてくることはあるまい)
と。
むやみやたらに兵を危険にさらさないことが百姓兵を指揮する者の常識であったからだ。
百姓兵の総帥たる義元とその幕僚たちは、信長軍とてそんな無茶な突撃を仕掛けてくることはありえない、と踏んだ。
(自分もそうであるから、他人もそうであるにちがいない)
と、考えるのは、常識的に考えることを常とするエリート秀才の陥り易い欠点のひとつかもしれない。
いや、ここまで来ると、
「そうあってほしい」(突撃しないでほしい)
という、願望の方が強かったかもしれない。
仮に万が一、二千の信長軍が今川本隊に突撃してきた場合を想定しても、それに対応した陣形を再度組み直すことは困難であった。
豪族連合の合議制で運営されていた今川軍では、その日の軍事行動は、前日前夜の戦評定で取り決められる。一旦取り決めたことを変更するには、また会議を興さねばならない。
もはや、そのような時間も余裕も無い。だから、そのこと(信長軍の突撃)を考えるだけで幕僚たちはゾッとした。
さらに、今川軍には不幸が重なった。
義元の勝利を確信していた土地の者たちが、陣中見舞いとして、酒や肴を差し入れてきたのである。
この日、桶狭間はことのほか暑かった。暑さのために、せっかくの“差し入れ”が腐ってしまう恐れがあった。そのため、今川本隊五千は、信長突入の危険を抱えつつも、休息をとり、腐る前に差し入れを食した。酒宴を開いてしまったのである。そのことが、災いに災いを重ねることとなった。
このあと、義元や幕僚たちが、考えたくもなかったことが、いよいよ現実のものとなる。
信長軍二千が、怒涛のごとく今川本隊に襲い掛かってきたのである。
今川本隊は慌てた。
本隊の前後に備えていた別働部隊が救援に駆けつけようとしたが、狭い道には本隊の荷車や軍馬がつかえ、酒に酔った兵たちが慌てふためいているだけで、近づこうにも近づけない。また、寸前まで降り続いた大雨のせいで道も周囲の泥田もぬかるんでいたのである。
それどころか、混乱が混乱を呼び、今川軍の同士撃ちまではじまる始末であった。
織田方、断然有利の状況だ。
とっさの命令系統が確立されていなかった合議隊の今川軍は狼狽し続ける。
ついに、兵のなかには敗走し始める者までいた。
それに対し、信長の命令一下、かれの育て上げた“落ちこぼれ集団”は果敢に攻め立てた。なにしろ、大将自ら前線で戦っていることが彼らをさらに刺激した。
あの弱隊の流浪兵たちが、必死で信長について行こうとしているのである。
信長は、うち捨てられた旗指物や、倒れた武将が身に着けている煌びやかな甲冑をみて、義元をすぐそこまで追い詰めていることを確信する。
かれは兵を鼓舞し、馬を煽って突進した。
のち、信長の家臣である毛利新介が義元の首を掠める。
戦いは、ごく短時間で決した。
因みに、信長はこの合戦における論功でも、それまでにない価値基準を導入する。まず従来なら、義元の首を獲った毛利新介が一番の功労者となる。が、信長はそうはしなかった。
一番手柄は、今川本隊が桶狭間にいる、という情報を信長に伝えた簗田政綱。
二番手柄は、戦場の中で義元本人を見つけた服部小平太。
そして、三番手柄に、義元の首をあげた毛利新介とした。
簗田が桶狭間情報を入手しなければ、服部の功労は無い。服部の功労が無ければ、毛利の功労もないのである。いかにも理にかなった価値基準である。
ともかくも、信長は勝つべくして勝った。
また、この戦いの結果は、信長が苦労して実現した組織改革とその成果に対する義元やその幕僚たちの無知と偏見の結末といっていい。
しかし、この改革の成果は留まることを知らない。
こうしたお金で雇いし傭兵方式が、さらなる組織効果を生み出すことになるのである。